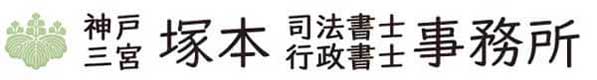こんな方にお勧めです。
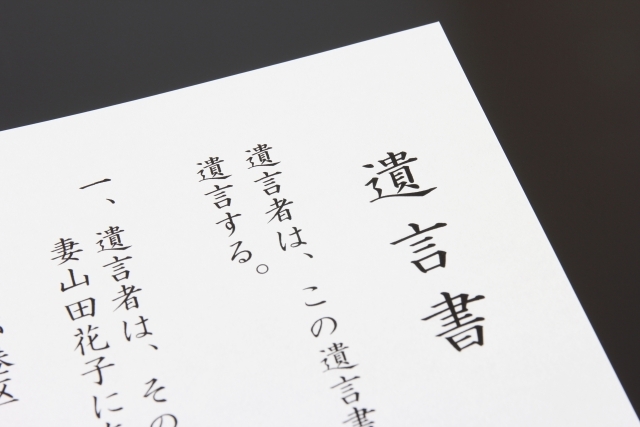
遺産分割協議サポートは相続人調査と一括での受任となります。戸籍等証明書・郵送料等の実費は別途必要です。上記は一例です。ケースにより報酬が加算される場合もあります。
遺言の検認とは
遺言の検認とは、すべての相続人に対して、遺言が存在すること、及びその内容を知らせるための手続。
また、検認当日の遺言書の状態(形状、日付、署名など)を記録して、遺言書の改ざん等を防止するための手続でもあります。
遺言が公正証書で作られていた場合には、検認手続は必要ありません。
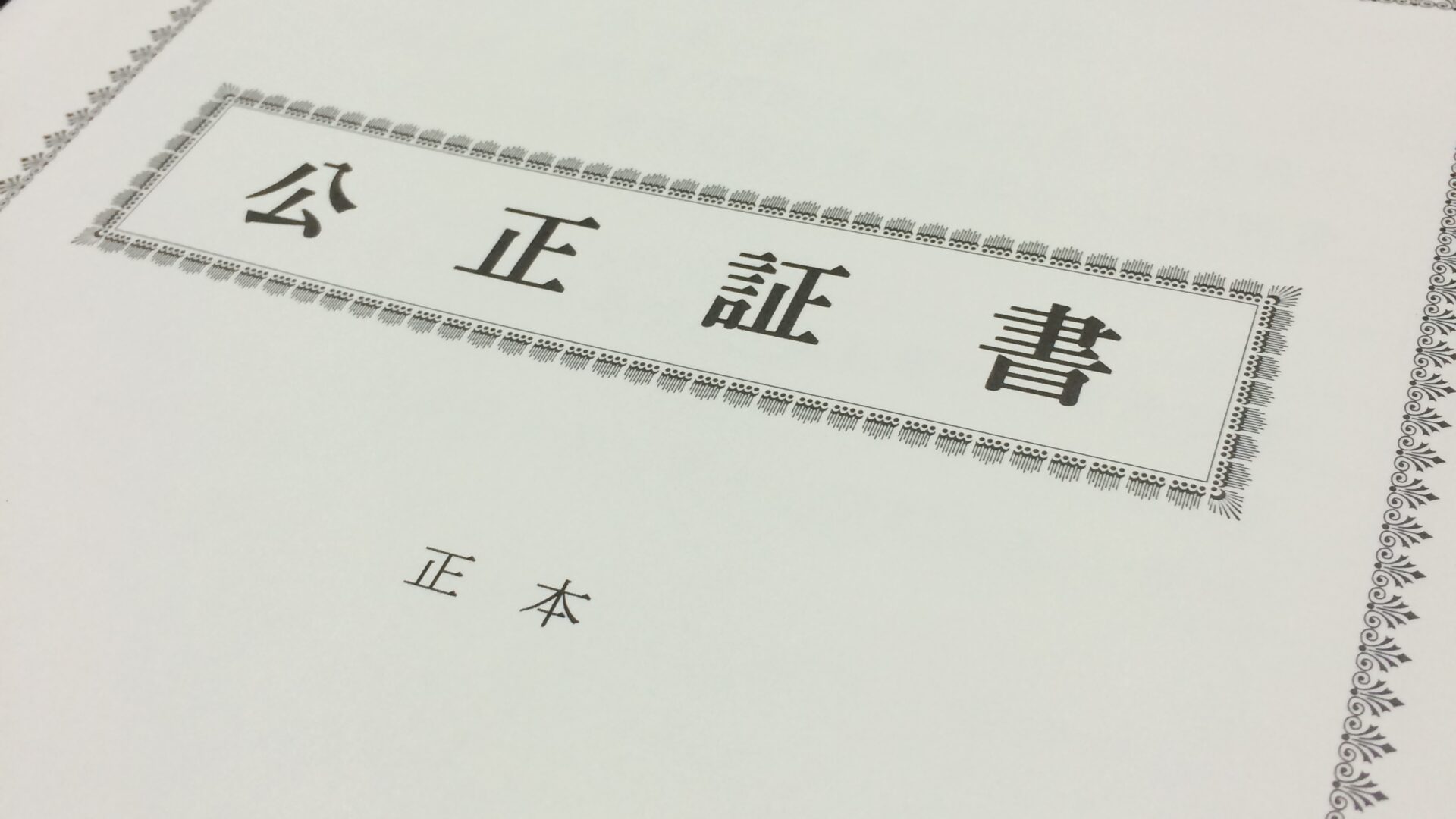
A4版の白い表紙の冊子で、表面に「公正証書」と大きく書かれています。
その場合には、遺言の内容を確認することも可能です。
しかし、遺言が自筆で書かれている場合には、家庭裁判所での遺言検認手続が必要。
検認手続を行っていない自筆証書遺言では、相続手続を進めることはできないのです。
令和2年7月10日から、自筆証書遺言を法務局で預かってもらう制度がはじまりました。
法務局に保管してもらっている自筆証書遺言の場合には、遺言の検認は必要ありません!
遺言書の検認
自筆証書遺言をつかって相続手続を行うには、遺言の検認手続が必要。
とはいえ、裁判所で遺言の検認手続を受けたからといって、遺言の有効・無効が判断される訳ではありません。
遺言の内容におかしな点がある場合には、検認手続とは別に、遺言の効力を争う裁判を起こすことになります。
遺言の検認についての法律の規定
(遺言書の検認)
第1004条
1.遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。2.前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3.封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
遺言の検認については、このような定めがあります。
公正証書が見つかったからといっても、封をされた自筆の遺言が別に存在する場合には、検認手続が必要です。
なぜなら、遺言が複数あって内容が相反する場合には、その部分について新しい遺言の方が効力を持つからです。
封をされた自筆の遺言の方が、公正証書よりも後に作成されている可能性もありますし、まったく別の内容の遺言が残されているかもしれません。
このことは、公正証書遺言の場合にもあてはまり、見つかった遺言が相当過去に作成されたものである場合には、新たに作成し直している可能性もありますので、最寄の公証役場で確認することをオススメします。
遺言の検認の方法
遺言の検認は、家庭裁判所への申立てによって行います。
遺言の検認の目的は、すべての相続人に、遺言の存在・その内容を知らせることですので、遺言検認の申し立ての前提として、相続人を確定させるための相続人調査が必要になります。
遺言検認申立てプランのサポート料金
費用に含まれるもの
- 相続に関するご相談
- 相続人調査・戸籍収集
- 裁判書類作成
- 裁判所への提出代行
費用に含まれないもの
- 印紙、郵券などの実費
- 戸籍、郵送料等の実費
- 出張を要する場合の出張費
被相続人1名・相続人5名を超える場合は、亡くなられている方1名あたり11,000円、相続人1名あたり3,300円の加算。